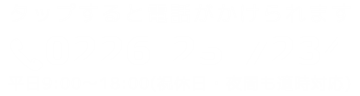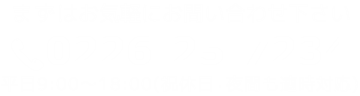【一関事務所】相続について その1
すごく久しぶりの記事になってしまいました。
ゆうちょ財団さん(https://www.yu-cho-f.jp/)の事業として,
気仙沼復興協会さん(http://kra-fucco.com/)の協力を得て,
気仙沼の仮設住宅をまわっての相談会というのに参加しています。
ただ,いきなり弁護士に相談といっても,相談しづらいこともあるようなので,
最近は,簡単なセミナーのようなものを開いて,法律の話をさせてもらってます。
以前,その中で,相続についての話をしたこともありますので,
そのときの内容を,何回かに分けて,ブログに再掲載します。
1
妻(夫)や親が亡くなったらその財産はどうなるのか?
誰が相続人かということと,その相続割合は,法律で決まっています。
たとえば,夫が亡くなって,妻と子一人だったら,その二人が相続人になります。
それぞれ,財産の半分ずつを受け取ることになるわけです。
これが,子二人だったら,妻が半分,子は四分の一ずつ。
他に,親や兄弟が相続人になることもあって,
親は,亡くなった者に子がいなければ相続権がありますし,
兄弟は,亡くなった者に,子も親もいなければ,相続権があります。
勘違いしやすいのは,妻(夫)が亡くなって,
子どもも孫もおらず,親もいないという場合でも,
夫(妻)だけが相続人になるわけではない,ということ。
この場合,夫(妻)とともに,兄弟も相続人になります。
ただしその割合は,夫(妻)が四分の三,兄弟は何人いても,兄弟全員で四分の一です。
2
今の民法では,法律上の相続割合は,
いわゆる「家督」は,関係がありません。
家督を継いだ子であっても,継がない子であっても,法律上の取り分は同じです。
3
では,子どもが親の面倒を見ていたり,介護していたら,取り分は多くなるでしょうか?
面倒を見ている分,取り分は多くなりそうだけど,実は,基本的には,法律上の取り分は同じです。
ただ,子どもが,親の生活費や介護費を支出していて,そのことによって,
親が財産の浪費を免れたというのであれば,その分,その子の取り分が多くなるという制度はあります(寄与分)。
しかし,支出していたという具体的な証拠がないことも多く,金額を算出するのが難しいことがあります。
4
一方で,逆に,子どもが親から特別な援助を得ていたらどうでしょうか?
たとえば,何人かいる子どものうち一人についてだけが,
生活費をたくさん援助されていたとか,事業資金を受け取っていたという場合。
この場合は,特別な援助を受けていた以上,その人の取り分が減るという制度があります(特別受益)。
ただ,この場合も,具体的な証拠がないことも多いです。
5
このように,法律上の相続割合は決まっていますが,
一方で,相続人の間で,話し合いによって,どのように遺産を分けるのか決めるのは自由です。
家督だから,この人は多く,とか,
今まで亡くなった人をお世話してくれた人については多く,とか,自由に決めることできます。
ただ,相続人全員が同意しないと,話し合いの効果が生じない,という難しさがあります。
6
話し合いによる解決ができない場合,どのように解決するか?
それは,次回の記事に書きたいと思います。
(同内容の記事をブログにも掲載してあります。)
ゆうちょ財団さん(https://www.yu-cho-f.jp/)の事業として,
気仙沼復興協会さん(http://kra-fucco.com/)の協力を得て,
気仙沼の仮設住宅をまわっての相談会というのに参加しています。
ただ,いきなり弁護士に相談といっても,相談しづらいこともあるようなので,
最近は,簡単なセミナーのようなものを開いて,法律の話をさせてもらってます。
以前,その中で,相続についての話をしたこともありますので,
そのときの内容を,何回かに分けて,ブログに再掲載します。
1
妻(夫)や親が亡くなったらその財産はどうなるのか?
誰が相続人かということと,その相続割合は,法律で決まっています。
たとえば,夫が亡くなって,妻と子一人だったら,その二人が相続人になります。
それぞれ,財産の半分ずつを受け取ることになるわけです。
これが,子二人だったら,妻が半分,子は四分の一ずつ。
他に,親や兄弟が相続人になることもあって,
親は,亡くなった者に子がいなければ相続権がありますし,
兄弟は,亡くなった者に,子も親もいなければ,相続権があります。
勘違いしやすいのは,妻(夫)が亡くなって,
子どもも孫もおらず,親もいないという場合でも,
夫(妻)だけが相続人になるわけではない,ということ。
この場合,夫(妻)とともに,兄弟も相続人になります。
ただしその割合は,夫(妻)が四分の三,兄弟は何人いても,兄弟全員で四分の一です。
2
今の民法では,法律上の相続割合は,
いわゆる「家督」は,関係がありません。
家督を継いだ子であっても,継がない子であっても,法律上の取り分は同じです。
3
では,子どもが親の面倒を見ていたり,介護していたら,取り分は多くなるでしょうか?
面倒を見ている分,取り分は多くなりそうだけど,実は,基本的には,法律上の取り分は同じです。
ただ,子どもが,親の生活費や介護費を支出していて,そのことによって,
親が財産の浪費を免れたというのであれば,その分,その子の取り分が多くなるという制度はあります(寄与分)。
しかし,支出していたという具体的な証拠がないことも多く,金額を算出するのが難しいことがあります。
4
一方で,逆に,子どもが親から特別な援助を得ていたらどうでしょうか?
たとえば,何人かいる子どものうち一人についてだけが,
生活費をたくさん援助されていたとか,事業資金を受け取っていたという場合。
この場合は,特別な援助を受けていた以上,その人の取り分が減るという制度があります(特別受益)。
ただ,この場合も,具体的な証拠がないことも多いです。
5
このように,法律上の相続割合は決まっていますが,
一方で,相続人の間で,話し合いによって,どのように遺産を分けるのか決めるのは自由です。
家督だから,この人は多く,とか,
今まで亡くなった人をお世話してくれた人については多く,とか,自由に決めることできます。
ただ,相続人全員が同意しないと,話し合いの効果が生じない,という難しさがあります。
6
話し合いによる解決ができない場合,どのように解決するか?
それは,次回の記事に書きたいと思います。
(同内容の記事をブログにも掲載してあります。)
2014年03月21日